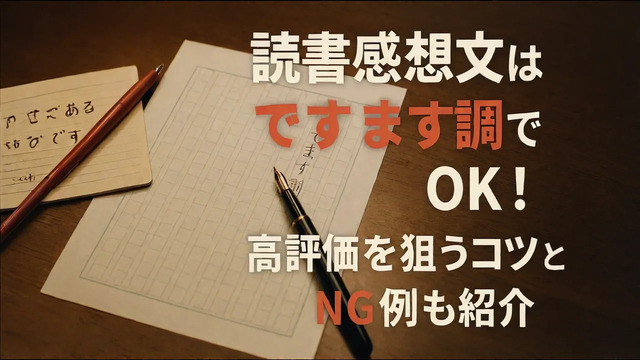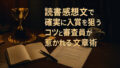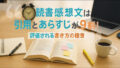読書感想文は、「ですます調」で書いても高く評価されます。
この文体は、読み手に対して丁寧さや親しみやすさを伝えることができ、特に小学生や中学生にとって適しています。
感情や考えを素直に表現しやすいため、読み手の心に届く文章に仕上がるのが大きな魅力です。
ただし、文体の途中変更や語尾の単調さには注意が必要です。
統一感のある文章であること、読みやすく整っていることが、評価のポイントになります。
また、原稿用紙での正しい使い方や、接続詞の選び方など、細かな部分まで意識すると、読み手にとってさらに伝わりやすい感想文になります。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 評価 | ですます調でも十分評価される |
| 向いている学年 | 小学生〜中学生に特におすすめ |
| 文体選びの基準 | 感情を伝える内容なら「ですます調」 |
| NGポイント | 文体の混在・単調な語尾・あらすじ過多 |
| 工夫点 | 語尾のバリエーション・丁寧な接続詞 |
| 原稿用紙の注意点 | 書き出し・段落・カギカッコの位置など |
ここでは、「読書感想文をですます調で書くべき理由」から、「文体の使い分け方」「よくある疑問とアドバイス」までを、
具体例・表・箇条書きを使ってわかりやすく解説しています。
じっくり読んで、自分らしい素直な読書感想文に仕上げてください。
読書感想文をですます調で書くべき理由とその効果
読書感想文をですます調(敬体)で書くべき理由と、その効果について詳しく解説していきます。
この文体がもたらす印象や、学年ごとのおすすめ文体の違い、読者への伝わりやすさなど、丁寧に掘り下げていきますね。
①「ですます調」が与える印象とは?
「ですます調」とは、文章の終わりを「〜です」「〜ます」でまとめる丁寧語の文体のことです。
この文体は、読み手に次のような印象を与えます。
| 印象 | 内容 |
|---|---|
| 親しみやすさ | 柔らかく、あたたかい雰囲気を与える |
| 丁寧さ | きちんとした印象があり、相手への配慮が感じられる |
| 分かりやすさ | 話し言葉に近く、小学生にも読みやすい |
特に読書感想文では、自分の気持ちや感動を表現することが多いので、「ですます調」の柔らかいトーンがぴったりなんですよね。
💡 ポイント:
- 小説の感想文やエッセイ風の文章に合う
- 読み手の「先生」や「親」にも好印象
②小学生に「ですます調」が向いている理由
小学生におすすめの理由は、次のように明確です。
✅ 理由一覧(箇条書き)
- 教科書や作文で普段から「ですます調」に慣れている
- 話し言葉に近く、書きやすい
- 自分の感情や感想を自然に表現できる
- 採点する先生が丁寧さを評価してくれる
さらに、学年別のおすすめ文体をまとめると以下のようになります。
| 学年 | 推奨文体 |
|---|---|
| 小学校低学年 | ですます調(一択) |
| 小学校中学年 | ですます調が基本だが、選択は自由に |
| 小学校高学年 | 内容次第で「だである」調も可 |
③中学生・高校生にも丁寧語が通用する場面とは
中高生になると、「だ・である調」を使いがちですが、「ですます調」が通用する場面もたくさんあります。
✅ 通用するシチュエーション:
- 感情を中心に語る内容
- 本の登場人物への共感を述べるとき
- コンクールや推薦入試向けで、読みやすさ重視のとき
- 家庭学習や自由提出の宿題
特に「〜と思いました」「〜に感動しました」といった表現は、やさしさや親しみを感じさせます。
| 文体 | 向いている場面 |
|---|---|
| ですます調 | 感情・印象を語る読書感想文 |
| だである調 | 批評・論理展開のある感想文 |
④読書感想文コンクールで選ばれる文体の傾向
実際に、読書感想文のコンクールではどちらの文体が多く選ばれているのでしょうか?
✅ 傾向としては以下の通りです。
| 学年 | 入賞作品に多い文体 |
|---|---|
| 小学生 | ですます調が主流 |
| 中学生 | だである調と混在もあるが、統一が重要 |
| 高校生以上 | だである調が多いが、ですます調でも入賞例あり |
また、「語尾がきれいにそろっている」「一貫した文体」が評価のポイントになっています。
❗ 混在(「です」→「である」など)は減点対象になることも!
入賞作品を読んでいると、文体うんぬんよりも、「素直な気持ち」がスッと伝わってくる作品が多いんですよね。やっぱり大事なのは中身です!
⑤読み手を意識した文体選びの大切さ
「読書感想文=自己表現」だけではなく、読み手(=先生や審査員)を意識することも大切です。
✅ 読み手にとっての読みやすさとは?:
- 語尾が統一されている
- 接続詞が自然で滑らか
- 感情が伝わりやすい
「〜なのだ」「〜だろう」「〜である」と断定されるよりも、「〜と思いました」「〜でした」の方が、柔らかくて親しみがあると感じる先生も多いです。
相手のことを思って書く文章は、それだけで心がこもって見えますよ〜!
⑥内容と文体の整合性を保つコツ
読書感想文でよくあるミスが、「内容は優しいのに、文体が固すぎる」というちぐはぐな印象です。
✅ 文体の選び方チェックポイント:
- 登場人物や感情に共感している →「ですます調」
- 事実・主張・分析が中心 →「だである調」
また、途中で文体が変わらないよう注意!
| 悪い例 | 良い例 |
|---|---|
| ぼくは感動した。とても心に残りました。 | ぼくは感動しました。とても心に残りました。 |
文章の「統一感」って、読み手にすごく伝わるんです。
最後まで同じ語り口で書くと、それだけで「上手だな」って思われやすいんですよね!
⑦「ですます調」を使った感想文の良い例
最後に、実際に「ですます調」で書かれた良い読書感想文の例を見てみましょう。
📘 例:『ごんぎつね』を読んで
私はこの本を読んで、正直とても悲しくなりました。
ごんが兵十に栗や魚を届けていたことを、最後まで兵十は知りませんでした。
自分の思いが届かないまま終わってしまうというのは、こんなにも切ないことなのだと感じました。
私も、ごんのように誰かにやさしくしたいと思っても、そのやさしさが伝わらなければ意味がないのだと気づきました。
この本を読んで、人とのつながりや気持ちを伝えることの大切さを学びました。
ね?こんなふうに「丁寧な語り口」って、感情が自然に伝わるんですよ~!
誰かの心に届くように書くには、「ですます調」ってやっぱり強い味方だと思います✨
読書感想文で「ですます調」と「だである調」を使い分けるコツ
読書感想文を書くとき、「ですます調」か「だである調」かで迷う人は多いはずです。
どちらを選んでも正解ですが、大切なのは内容に合った文体を選び、統一することなんです。
この章では、それぞれの文体の違いや、年齢に応じた使い分け、そして実例まで詳しく解説していきますね。
①両者の違いと基本的な特徴
「ですます調」と「だである調」は、文章の語尾の形による違いですが、その印象や読み手への伝わり方は大きく異なります。
| 文体 | 特徴 | 向いている表現 | 読者に与える印象 |
|---|---|---|---|
| ですます調 | 敬体。丁寧でやさしい | 感想・共感・思い | やわらかい・親しみやすい |
| だである調 | 常体。断定的・硬め | 主張・分析・批評 | 論理的・強い |
「ですます調」は、やさしい語り口で感情を表現したいときにぴったりなんです。
一方で、「だである調」は、ぐっと引き締まった印象になりますよね〜。
②学年別での使い分け方の目安
文体の選び方は、学年や学習レベルによってもおすすめが変わります。
✅ 文体の使い分け早見表:
| 学年 | 推奨文体 | 理由 |
|---|---|---|
| 小学校低学年 | ですます調 | 教科書や話し言葉に近く書きやすい |
| 小学校中学年 | ですます調 or 両方 | 慣れている方を選べる時期 |
| 小学校高学年 | だである調もOK | 主張を書く力がつき始める |
| 中学生以上 | だである調 | 学術的・論理的な文章が求められる |
もちろん学校の方針にもよりますが、個人的には「自分の素直な言葉で書きやすい方」を選ぶのが一番だと思いますよ。
③「混在」はなぜNGなのか?
文体の混在(例:「…と思いました。~である。」など)は、読み手に違和感を与えてしまいます。
❌ 混在の例(NGパターン)
この本を読んで驚いた。とても心が動きました。→×(常体と敬体の混在)
✅ 統一された例(OKパターン)
この本を読んで驚きました。とても心が動きました。→〇(敬体で統一)
この本を読んで驚いた。非常に印象的である。→〇(常体で統一)
🚨混在がNGな理由
- 一貫性がなく、読みづらい
- 文章の「質」が低く見える
- 評価を下げられる原因になる
コンクールや先生のチェックでは、「文体が統一されているか」はかなり見られます!
ほんと、ここは気をつけてくださいね〜。
④自分に合った文体を選ぶための判断基準
自分にとって、どちらの文体がしっくりくるかを判断するには、いくつかのポイントがあります。
✅ 判断のポイント:
- 感情を中心に伝えたい → ですます調
- 意見や考察をはっきり述べたい → だである調
- 普段から使い慣れている文体はどっち?
- 提出先(学校やコンクール)の方針は?
私は、テーマが「感動」や「学び」だったら、迷わず「ですます調」派。
逆に、社会問題に絡んだ本だと「だである調」がしっくりきます。
⑤「だである調」が向いているテーマや本とは
では、どんな読書感想文なら「だである調」が向いているのでしょうか?
📘 向いているテーマ・ジャンル:
- 歴史書・ノンフィクション・評論
- 社会問題を扱う小説
- 学問的・倫理的な考察を求められる本
- 推薦文やリポートに近い内容
| 作品例 | おすすめ文体 |
|---|---|
| 『夜と霧』 | だである調 |
| 『沈黙』 | だである調 |
| 『人間失格』 | だである調(深い内省あり) |
断定して書きたいときには「だである調」がしっくりきますよね〜!
「強く伝えたい!」ってときにはこれです。
⑥「ですます調」でありがちな語尾の単調さを防ぐテクニック
「です」「ます」ばかりになってしまうと、文章が単調で飽きやすくなってしまいます。
✅ 単調さを防ぐコツ
- 接続詞や文のリズムを工夫する
- 感情表現のバリエーションを増やす
- 文末を「〜でした」「〜だと思います」「〜ように感じました」などと変える
- 体言止めを適度に入れる(例:…だったのです。悲しみ。)
📚 接続詞の例
| 接続詞 | 用途 |
|---|---|
| しかし | 対比・逆説 |
| たとえば | 例示 |
| なぜなら | 理由の説明 |
| そのため | 結果の説明 |
語尾って意外と目立つんですよね〜。
だからこそ、ちょっとだけ工夫するだけで、「この子、文章上手だな!」って思われることも多いですよ。
⑦実例で見る!文体による印象の違い
最後に、同じ内容を「ですます調」「だである調」で比較してみましょう。
🎓テーマ:「星の王子さま」を読んで:
| 文体 | 実例 |
|---|---|
| ですます調 | 私はこの本を読んで、心がとても温かくなりました。王子さまの純粋な言葉に、何度も胸を打たれました。大人になっても、子どもの心を忘れないようにしたいと思いました。 |
| だである調 | この本を読み、心が温まった。王子の純粋さが胸に響いた。大人になっても、子どもの視点を持ち続けることが大切であると感じた。 |
📌 印象の違い:
- 「ですます調」はやさしく感情に寄り添う
- 「だである調」はシンプルで断定的、論理的
ほんとに印象がガラッと変わるんですよ!
自分の伝えたい「気持ち」や「考え方」に合わせて文体を選んでくださいね!
読書感想文 ですます調に関するよくある疑問とアドバイス
「読書感想文は“だである調”が良いって聞くけど、“ですます調”でも大丈夫かな……?」
そんな疑問を持つ方は多いと思います。
ここでは、よくある質問への答えと、先生やコンクールを意識した具体的なアドバイスをまとめました。
①「ですます調」でも評価される?
結論から言うと──評価されます!
文体で評価が決まることはありません。
大切なのは中身と統一感。
| 評価される要素 | 内容 |
|---|---|
| 思いや感情がしっかり伝わっているか | 文章に心がこもっているか |
| 文体が最後まで統一されているか | 途中で混ざっていないか |
| 読みやすいか | 接続詞や改行も重要 |
📌 こんな作品が高評価を受けやすい
- 登場人物への感情移入が深い
- 本を通じて得た“学び”が書かれている
- 丁寧な言葉で、伝える力がある
私の生徒でも、「ですます調」で書いた子が何度も入賞してますよ〜!
やさしい語り口は、むしろ武器になります。
②原稿用紙での使い方と書き出しのコツ
いざ書こうとすると、原稿用紙の使い方で悩むことも多いですよね。
✅ 原稿用紙の基本ルール(400字詰め)
- 書き出しは1マス空けて始める
- 段落の最初も1マス空ける
- 会話や引用は「カギカッコ」で囲み、前後に1マス空ける
- 改行も意識して、読みやすさアップ
✍ 書き出しの例(「ですます調」)
『星の王子さま』という本を読んで、とても心が温かくなりました。
この本を選んだ理由は、表紙のイラストにひかれたからです。
NG例:
私がこの本を選んだ理由は……
→ありきたり&作文っぽい印象になりやすい
「いかにも宿題」みたいな書き出しは避けて、自然な自分の言葉から始めるといいですよ〜!
③コンクール応募時に注意すべきこと
読書感想文をコンクールに出す場合、特に気をつけたいポイントがあります。
✅ 注意ポイント:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 文体の統一 | 「ですます」調で最後まで揃っているか? |
| 語尾の工夫 | 単調にならず、バリエーションがあるか? |
| 感想中心か? | あらすじばかりになっていないか? |
| 本から得た“学び”があるか? | 単なる感情だけで終わっていないか? |
| 見直しをしているか? | 誤字・脱字、句読点の使い方など |
特に「提出前の読み直し」はめちゃくちゃ大事!
1日寝かせてから読み直すと、自分でも「ここ変だな~」って気づけたりします。
④先生に相談しておくと安心なポイント
学校の課題として出す場合、先生によって文体や内容の好みが違うこともあります。
✅ 事前に聞いておきたいこと:
- 「文体(ですます調)でもいいですか?」
- 「何文字くらいが目安ですか?」
- 「原稿用紙は何枚提出ですか?」
- 「評価のポイントはありますか?」
聞いておくことで、不安や迷いが減りますよ〜!
先生も「おっ、やる気あるな」と思ってくれるかもしれません(笑)
⑤「敬体」にふさわしい接続詞の選び方
「ですます調」を使うときは、丁寧な接続詞も一緒に使うと、文章がさらに自然になります。
📚 よく使われる接続詞(ですます調に合うもの)
| 接続詞 | 用途・ニュアンス |
|---|---|
| しかし | 軽い逆接(やさしい印象) |
| それに | 追加情報を伝えるとき |
| たとえば | 例を示すとき |
| なぜなら | 理由を丁寧に説明したいとき |
| そのため | 結果を導くとき |
NGな接続詞:
- 「だが」「よって」「ゆえに」など → やや硬すぎる印象
「接続詞」って、地味だけど文章の流れをスムーズにするキーマンなんですよ〜!
⑥文章全体に一貫性をもたせるには
文章に“まとまり”がないと、読み手に「何を伝えたいの?」と思われてしまいます。
✅ 一貫性をもたせるポイント:
- 最初にテーマ(読後の感情や気づき)を決める
- 各段落でそのテーマに沿った話を展開
- 「感動した」「共感した」「学んだ」のどれかに軸を置く
- 文体(ですます調)を一貫して使う
📝 構成のテンプレート(ですます調・原稿用紙5枚分):
| 段階 | 内容 | 目安文字数 |
|---|---|---|
| ① 本を選んだ理由 | 300字程度 | |
| ② 登場人物について | 600字程度 | |
| ③ 印象的な場面と自分の気持ち | 600字程度 | |
| ④ 本から得た学び | 500字程度 |
「この本を通じて、私は〇〇を学びました」とまとめると、読後感がぐっと良くなりますよ!
⑦語尾を工夫して読ませる文章にしよう
「~です。」「~ます。」だけでは、どうしても単調になりがちです。
読み手の心をつかむためには、語尾にも変化をつけていきましょう。
✅ 語尾バリエーション例:
- ~でした
- ~ように思いました
- ~と感じました
- ~したいと思いました
- ~ようにしたいです
- ~のではないでしょうか
- ~だと私は考えています
📌 例文:
この言葉に私は強く共感しました。
だからこそ、今後の自分にも活かしたいと思ったのです。
自分の行動を少しずつでも変えていきたいと感じました。
「です・ます」だけに頼らず、「思いました」「感じました」「考えました」などを織り交ぜると、グッと大人っぽくなりますよ〜!
読書感想文はですます調でOK!高評価を狙うコツとNG例のまとめ
読書感想文は、やさしさと丁寧さを伝えやすい「ですます調」で書いても、しっかりと評価されます。
特に小学生〜中学生にとっては、自然に気持ちを表現できる文体として非常におすすめです。
ただし、評価されるためには次のような点に注意が必要です。
✅ 高評価を得るためのチェックポイント
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 文体の統一 | 最初から最後まで「ですます調」で書く |
| 語尾の工夫 | 「〜です」「〜ました」ばかりにしない |
| 接続詞 | 丁寧な印象の接続詞を選ぶ(たとえば・そのため など) |
| 内容の構成 | あらすじよりも感想・気づき・学びを重視 |
| 書き出し・原稿用紙の使い方 | 冒頭の1マス空け・段落の統一・カギカッコの使い方など |
| 事前確認 | 提出前に先生や保護者に相談しておくと安心 |
✅ こんな方に「ですます調」はおすすめです
- 感情をやわらかく伝えたい
- 読み手に親しみを持ってもらいたい
- 自分の言葉で素直に書きたい
- 初めての読書感想文で不安がある
読書感想文は、自分の気持ちをまっすぐに届ける文章です。
「ですます調」で書くことで、やさしさや思いやりが読み手に自然と伝わります。
ぜひ、文体も自分らしさの一部として、大切に選んでみてくださいね。