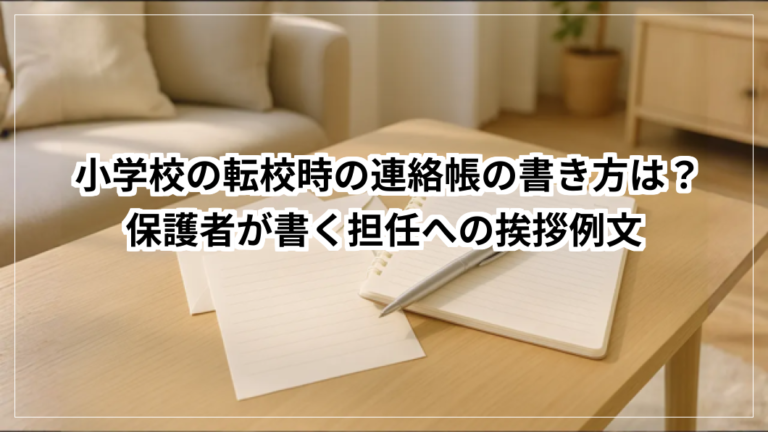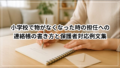小学校の転校時に連絡帳で担任へ挨拶を伝える際は、まず「転校が決まりそうな段階」で一報を入れ、
正式に決まったら改めて「転校確定の連絡」と「お礼の挨拶」を記載するのがマナーです。
保護者としては、転校の理由・引越し時期・新しい学校名などの基本情報に加えて、
子どもの気持ちや学校生活への配慮も併せて伝えると、先生の理解と対応がスムーズになります。
結論からお伝えすると、
-
連絡帳での報告は「決まりそうな時点」と「正式決定後」の2回が基本
-
丁寧かつ簡潔に、事実・予定・感謝を明確に記載すること
-
子どもの心情や状況に関する一言を添えると先生の配慮も得やすい
-
プレゼントは不要だが、感謝の言葉や気持ちを大切に
-
文章例はテンプレをベースに、自分の言葉で自然にカスタマイズ
以上の点を押さえることで、担任の先生との信頼関係を保ったまま、スムーズな転校準備ができます。
本記事では、小学校の転校時に保護者が連絡帳で担任へ挨拶をする正しい方法と例文、伝えるべきタイミングやマナーまでを網羅的に解説しています。
このあと本文では、実際に使える連絡帳の例文、挨拶のマナー、クラスメイトやママ友への配慮、転入先での準備まで、
保護者として「これだけは知っておきたいポイント」を具体的に解説していきます。
じっくり読みたい方は、ぜひ続きをご覧ください。
小学校の転校で連絡帳に書く内容と例文集
小学校の転校で連絡帳に書く内容と例文をまとめてご紹介します。
特に保護者が担任の先生に連絡帳で伝えるべきことは、タイミングや内容によって微妙に変わってきますよね。
ここでは「転校が決まりそうなとき」「転校が決まったとき」の2パターンに分けて、丁寧で失礼のない伝え方と、すぐに使える例文を紹介していきます!
①転校が決まりそうなときの書き方
転校が「決まりそう」な段階では、まだ正式な辞令や引越しの確定が出ていないことが多いですよね。
この段階で担任の先生に伝えるべきか、迷う保護者の方も少なくありません。
ですが、早めに情報を共有しておくことで、先生側の心づもりができるため、子どもの新しい環境への橋渡しもスムーズに進む可能性が高くなります。
連絡帳で伝えるときは、「あくまでも未確定」というニュアンスを大切にしながらも、
丁寧にお願いする姿勢を見せるのがポイントです。
たとえば、こんな文例はいかがでしょうか?
【連絡帳の例文(転校が決まりそうなとき)】
いつもお世話になっております。
まだはっきりとはしていないのですが、夫の仕事の都合で来学期から転居する可能性が出てまいりました。
確定次第、改めてご報告させていただきますが、念のためご報告申し上げます。
今後のことで何かご相談させていただくことがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
このように書くことで、「まだ確定していないが、可能性がある」という微妙な段階でも、
誠実な印象を与えられます。
ちなみに我が家のときは、転勤の“内示”が出た段階で、すぐに連絡帳に書いて先生にお知らせしました。
ちょっと早すぎるかな?と心配もあったんですが、先生からは「早めに教えてくださって助かります」と感謝されましたよ!
保護者同士の情報共有もあるので、先生には一番に伝えるという意識が大切です。
早めの準備が、子どもにとっても安心に繋がりますよね♪
②転校が決まったときの書き方と伝え方
いよいよ転校が正式に決まったら、すぐに担任の先生へしっかりとご報告しましょう。
このとき、連絡帳だけでなく、可能であれば直接お会いして伝えるのが理想ですが、
平日の朝や夕方は忙しくてタイミングが合わないことも。
そんなときは、連絡帳で丁寧に伝えておくと安心です。
ここで大切なのは「転校が確定したこと」と「お礼の気持ち」をしっかり含めることです。
【連絡帳の例文(転校が決まったとき)】
いつも大変お世話になっております。
このたび、○月末に夫の転勤により引越しが決まり、〇〇(市区町村)の小学校へ転校することになりました。
子どももクラスの皆さんと離れるのが寂しいようですが、最後まで楽しく過ごせるようサポートしたいと思います。
短い間ではありましたが、先生には大変お世話になり、心より感謝しております。
転校に関する手続き等、ご指導いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
このように、丁寧な言葉と感謝の気持ちを込めた文面を心がけましょう。
もし余裕があれば、手書きの手紙やちょっとしたお礼の品(市販のお菓子など)を添えると、
より気持ちが伝わります。
ちなみに、わたしの知人は「めんべい(福岡名物)」を渡したそうですが、先生も「珍しくてうれしい!」と喜ばれたそうですよ~!
大事なのは形式よりも「気持ち」。
あたたかく、誠意を持って伝えれば、それだけで十分です😊
③連絡帳に書くべきタイミングと注意点
転校に関する連絡を「いつ書くか」は、実はとっても重要なポイントなんです。
タイミングを間違えると、先生に迷惑をかけてしまったり、子どもの環境にも影響が出てしまうことがあるので要注意です。
基本的には、引越しが「決まりそう」な段階で一度、正式に「決まった」らすぐに再度伝える、この2ステップがベスト。
学校側も転校生への対応準備(書類作成、成績処理、クラス替え調整など)がありますから、早めに伝えることで先生の負担もグッと減ります。
【おすすめのタイミング】
| 状況 | タイミング | 手段 |
|---|---|---|
| 内示が出た | なるべく早く(1ヶ月前目安) | 連絡帳または口頭 |
| 転校が確定した | 決定したその日 or 翌日 | 連絡帳&口頭 or 電話 |
| 書類受け渡し | 終業式や面談時 | 直接手渡し |
そして、書くときの注意点としては以下の3つが大切です。
これだけで、印象がぐんと良くなりますよ♪
個人的な経験談ですが、連絡が遅れてしまった知人がいて、先生から「もっと早く知りたかった」と言われて落ち込んでました…。
だからこそ、“思い立ったら即連絡帳”が合言葉くらいでちょうどいいと思います!
④担任の先生との連絡手段は連絡帳だけでOK?
転校の連絡手段として、いちばん使いやすいのが「連絡帳」なのは間違いありません。
でも、連絡帳だけで済ませてしまっても大丈夫なのでしょうか?
結論から言うと、連絡帳だけでも最低限の連絡は可能です。
ただし、それだけだと行き違いが起きる可能性もあるので、できれば口頭や電話でのフォローも忘れずに行うと安心です。
【連絡手段ごとのメリット・デメリット】
| 手段 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 連絡帳 | 手軽・記録に残る | 誤解が生まれやすい |
| 直接面談 | 表情が見える・丁寧な印象 | 時間が必要 |
| 電話 | 早い・その場で質問可 | 担任が出られないことも |
特に大事な書類や日程の確認は、二重の連絡手段を意識しておくとミスが防げます。
また、最近は連絡帳の内容を口頭で補足する保護者の方も増えていて、
「◯日に連絡帳でお知らせした件ですが…」と、放課後に少し話しかけるのも好印象です。
わたし自身、最初は連絡帳だけに頼ってましたが、いざ先生に会って話してみると、
「あ、やっぱりちゃんと話すって大事だな」と実感しました。
伝わった“つもり”にならないようにしたいですよね!
⑤保護者として伝えるべきポイントとは
転校の連絡を書くとき、「何を伝えれば十分?」と迷う方、多いですよね。
でも安心してください。大事なのは最低限の情報+感謝の気持ちをしっかり伝えることなんです。
以下のようなポイントを押さえておけば、どんな状況でも落ち着いて対応できますよ。
この中でも「感謝」はとくに忘れがちですが、とても大切なポイントです。
先生方は日々たくさんの子どもを見ていますが、
その中で「心を込めて育ててくれた保護者だな」と感じてもらえるだけで、印象が大きく変わります。
そして、連絡帳の文面は必要最低限+あたたかい言葉でまとめるのが理想です。
わたしが書いたときは、「先生のおかげで本人も楽しく学校生活を送ることができました。本当にありがとうございました」と締めくくりました。
ほんの一言が先生の心に残ること、ありますよね。
「形式じゃなくて、“想い”が大事」って、ほんと実感します…!
⑥子どもへの配慮をどう伝えるか
転校という大きな出来事は、子どもにとって想像以上のストレスや不安を伴うものです。
保護者としては、連絡帳の中でも担任の先生に「子どもへの配慮」をお願いしておくと、
学校生活の安心感につながります。
ここでは、実際に先生に伝えておくと良いポイントや、連絡帳での書き方を紹介していきます。
先生に伝えておきたい「子どもへの配慮」リスト
-
転校について本人がどう受け止めているか(例:不安が強い、楽しみにしている)
-
情緒面での変化(例:最近涙もろい、朝なかなか起きられない)
-
仲の良い友達との関係(例:別れを惜しんでいる様子)
-
最終登校日がいつになるか(例:この日まで通う予定です)
-
お別れ会や発表の場があるかどうかの相談
たとえば、連絡帳ではこういった書き方ができます👇
転校が決まり、本人は少しずつ受け入れようとしている様子ですが、時折「みんなと別れるの寂しいね」と話しています。
できるだけ楽しく最後まで学校に通えるよう、先生にも温かく見守っていただけますと幸いです。
先生は限られた時間のなかでたくさんの子どもを見ていますから、こうした情報があると、より深く丁寧に対応してくださることが多いです。
ちなみに私の娘も、引越し前の1週間はちょっとナーバスになっていて…「給食が終わったら急に泣いちゃった」なんてこともありました。
先生にあらかじめ伝えていたおかげで、教室で静かに休ませてくれたり、そっと声をかけてくれたりして、とても助かりましたよ。
子どもの気持ちに寄り添う姿勢、先生と一緒に作っていけたら安心ですね☺️
⑦実際に使える例文まとめ(コピペOK)
ここまでたくさんのポイントを紹介してきましたが、最後にまとめとして、そのまま使える連絡帳の例文を用途別にご紹介します!
「うまく言葉が出てこない…」「丁寧な表現って難しい…」というときの参考に、ぜひ活用してくださいね。
転校が決まりそうなときの例文
いつもお世話になっております。
現在のところ未定ではありますが、来月以降に転勤の可能性が出てまいりました。
確定ではございませんが、念のためご報告させていただきます。
詳細がわかり次第、改めてお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。
転校が正式に決まったときの例文
いつもご指導いただきありがとうございます。
このたび〇月〇日をもって、○○市への転居が決まり、○○小学校へ転校することとなりました。
本人はクラスの皆さんと離れるのが寂しいようですが、最後まで楽しく通えるようサポートしてまいります。
これまでのご指導に心より感謝申し上げます。
今後の手続き等につきまして、ご指導いただけますようお願いいたします。
子どもへの配慮をお願いしたいときの例文
転校が近づく中で、本人も少しナーバスになっている様子があります。
笑顔で登校できるよう、なるべくいつも通りに過ごせるように心がけておりますが、もし授業中などに様子がおかしいと感じられることがありましたら、ご配慮いただけますとありがたいです。
いずれの例文も、「敬意」と「感謝」を忘れずに入れることで、どんな状況でも好印象を持っていただけますよ。
わたしも過去に何度かこのテンプレを使いましたが、そのたびに先生から「とても丁寧で嬉しかったです」と言っていただけました!
迷ったらこの例文からアレンジして、自分の言葉にしてみてくださいね😊
担任への挨拶を保護者が書くときのマナーと例文
担任への挨拶を保護者が書くときのマナーや、実際に使える例文について詳しく紹介します。
小学校の転校は、子どもにとっても大きなイベントですが、同じくらい大切なのが、先生方への感謝をきちんと伝えることです。
ここでは、丁寧で失礼のない言い回しや、お礼の気持ちの込め方など、知っておきたいポイントを具体的に解説しますね。
①丁寧で失礼のない表現のコツ
「どんな言葉を選べば失礼にならないか…」って、意外と悩みますよね。
特に学校関係の文面は、丁寧にしすぎて堅苦しくなったり、逆にカジュアルになりすぎたりと、バランスが難しいところ。
でも大丈夫。
大切なのは「簡潔で、気持ちが伝わること」なんです。
【丁寧で失礼のない表現テク】
-
「ご指導いただきありがとうございました」
→「ご指導いただき、心より感謝申し上げます」 -
「お世話になりました」
→「日頃より温かくご対応いただき、本当にお世話になりました」 -
「よろしくお願いします」
→「何卒よろしくお願い申し上げます」 -
「すみません」より「恐れ入りますが」などを使うと◎
-
「とても助かりました」→「日々のご配慮に、深く感謝いたしております」
こういった表現を使うことで、品のある印象を保ちつつ、
しっかりとした感謝の気持ちが伝わります。
それから、連絡帳に書く場合は1~2段落にまとめるのが読みやすくておすすめです。
わたしの場合は、こんなふうに書きました👇
いつもあたたかくご指導くださり、本当にありがとうございます。
このたび転校が決まりましたので、ご報告申し上げます。
突然のことでご迷惑をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。
かしこまりすぎず、でも礼儀正しく。
この“ちょうどいい距離感”が大事なんですよね。
②お世話になったお礼の気持ちの伝え方
「担任の先生へのお礼って、どのくらい丁寧にすればいいの?」
そう感じている方も多いと思いますが、基本は“言葉で伝えること”が何より大切です。
モノより気持ち。これはどの先生にも共通して響くポイントです。
【感謝を伝えるときに押さえておきたい3つの柱】
-
「具体的なエピソード」をひとつ入れる
→例:「登校渋りがあった際も、温かく対応いただきありがとうございました。」 -
「子どもが変化した点」に触れる
→例:「学校が楽しい!と毎日笑顔で帰ってきました。」 -
「先生のおかげ」という言葉を添える
→例:「先生のおかげで、大きな自信になったようです。」
文面にすると、こうなります👇
これまで温かいご指導を賜り、誠にありがとうございました。
入学当初は不安げだった我が子も、先生のおかげで毎日明るく登校することができました。
いつも笑顔で迎えてくださり、子どももとても信頼しておりました。
短い間でしたが、大変お世話になりましたこと、心より御礼申し上げます。
先生にとっても、こうしたメッセージは「この仕事をやっていて良かった」と思える瞬間だそうです。
わたしの友人も、「担任の先生に手紙を渡したら涙ぐんでくれて…」と話していて、その後もしばらくやり取りが続いていたそうですよ😊
気持ちのこもった言葉は、ずっと残る贈り物になります。
③先生が知っておくべき情報の整理法
転校の際、担任の先生にお伝えする情報って、意外と多くて「何をどこまで?」と迷ってしまいがちですよね。
でも実は、先生にとって本当に知っておいてほしいことって、ある程度パターン化されているんです。
ここでは「連絡帳や口頭で伝えるべき内容」を、分かりやすく整理してみました。
【担任の先生に伝えるべき基本情報】
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| 引越し日・転校予定日 | ○月○日ごろを予定しています |
| 転校理由 | 夫の転勤・住宅購入など簡潔に |
| 新しい学校名 | ○○市立△△小学校(未定でもOK) |
| お別れの日程 | 最終登校日は○日になる予定です |
| 子どもの心境や変化 | 緊張・不安などあれば共有を |
| 手続き関連のお願い | 必要書類についての確認依頼 |
とくに「子どもの心境」は、忘れずに伝えておきたいポイント。
たとえば、「最近少しナーバスです」と一言添えるだけでも、先生が気にかけてくれるきっかけになります。
そして、1回の連絡帳で全部書く必要はありません!
分けて伝えてもまったく問題ありませんので、焦らず丁寧に1つずつ伝えていきましょう。
我が家では、最初の連絡帳では転校の報告だけにして、翌週に「最終登校日の相談」と「子どもの様子」を追加で書きました。
先生も、「段階的に教えてもらえて助かりました」と言ってくれて、ホッとしたのを覚えてます😊
④直接挨拶に行く場合の服装と持ち物
「連絡帳で挨拶したけど、やっぱり直接も行った方がいい?」
そう思う方、けっこう多いんじゃないでしょうか?
実は、直接の挨拶が必須というわけではないんですが、行けるなら行った方が、やっぱり心のこもった印象になります。
ではその際、どんな服装・何を持って行けばいいの?という点について、解説しますね。
おすすめの服装(親)
-
参観日や懇談会レベルのカジュアルきれいめ
→ワンピースやパンツスタイルにカーディガンなど -
TPOに合った清潔感のある装い
-
派手な色・装飾は避ける
持ち物リスト
| 持ち物 | 用途 |
|---|---|
| 手紙または連絡帳 | あいさつ用の一言メッセージを添えると◎ |
| 菓子折り(必要に応じて) | 地域により差あり。1000円〜1500円程度が目安 |
| 上履き・スリッパ | 職員室や教室に入るとき用 |
| 子どもの上靴(持ち帰り用) | 最終登校日なら必須です! |
ちなみに私が訪問したときは、菓子折りに「地元のお菓子詰め合わせ」を持っていきました。
「公務員だから贈り物はダメかな?」と不安でしたが、1000円前後のものであれば、
「お気持ちとして受け取りますね」と快く対応してくださいましたよ!
あくまでも感謝の気持ちを形にしたものとして渡せば、無理のない印象になります。
⑤連絡帳で伝えること・伝えないこと
連絡帳は便利なツールですが、だからこそ「何でも書いていい」わけではないんですよね。
書くべきことと、書かない方がいいこと。この“線引き”が意外と大事なんです。
ここでは、連絡帳で伝えるべきこと・避けたいことを整理してみました👇
たとえば、「実は夫の転勤が急でバタバタで…ほんと大変で…」みたいな話は、感情が乗りすぎてしまい、先生も対応に困ってしまうことがあります。
あくまでも、事実を明確に、感情は控えめに、でも温かさを忘れずに。
私が書いたときも、「家庭の事情が急変して…」とは書かずに、「転勤が決まりましたので、お手続きのご相談をお願いできますでしょうか」とだけ伝えました。
そうすることで、信頼関係を保ちながらスムーズなやり取りができましたよ!
⑥菓子折りや贈り物はどうする?
「先生にお世話になったし、何か渡した方がいいのかな?」
この疑問、ほんとによく聞かれます!
でも実際のところ、“渡す・渡さない”には明確なルールはありません。
地域差や学校の方針にもよりますし、「絶対必要」ではないんです。
とはいえ、気持ちとして何か渡したいという場合には、常識の範囲内での“感謝のしるし”として受け取っていただけるケースが多いですよ。
【おすすめの贈り物&選び方】
| 品物 | おすすめポイント |
|---|---|
| 菓子折り(個包装) | 教員室で分けやすい・価格も手頃(1000~1500円程度) |
| 地元の名物 | 話題にもなる・印象に残りやすい |
| 手紙+プチギフト | 感謝の気持ちを言葉でも形でも伝えられる |
| ハンカチや文具 | 実用性が高く、無難で失礼がない |
実際にわたしが選んだのは、「福岡名物のめんべい(個包装)」でした!
担任の先生が九州出身ということで、とっても喜んでくださって。
「懐かしい味です~」と盛り上がったのを覚えています😊
ただし、先生方は公務員なので、高価すぎる品や現金・商品券などはNGです!
あくまでも「ちょっとした気持ち」として、
無理のない範囲で“感謝を形にする”というスタンスがおすすめです。
あと、名前入りの手紙を添えると、ぐっと印象が良くなりますよ♪
⑦担任との関係を円満に終えるポイント
最後に大切なのが、「去り際の印象」です。
転校は一つの区切りではありますが、だからこそ保護者として、最後まで気持ちよく終えることを意識したいですよね。
ここでは、担任の先生と円満に関係を終えるためのコツをお伝えします。
【円満にお別れするための3つのポイント】
-
最終登校日のあいさつをしっかりと
→「本日が最後の登校になります。これまで本当にありがとうございました。」 -
感謝の手紙を添える
→短くてもOK。「先生のご指導が励みになりました」などの一言が心に残ります。 -
お別れのタイミングでバタバタしない工夫
→持ち物の整理や下校時間の確認など、事前準備を忘れずに。
それと、先生が一番うれしいのは、「この子を見てきてよかったな」と思えるような一言なんです。
わたしは最後の連絡帳にこんな一文を添えました。
先生のおかげで、〇〇も毎日がんばる楽しさを学ぶことができました。
本当にありがとうございました。
それに対して、先生から「私こそ、〇〇さんの頑張る姿に毎日元気をもらっていました」と返信をもらって…もう涙でした…。
お世話になったことへの感謝と、丁寧なお別れの挨拶。
それだけで、十分素敵な“円満な関係”になります。
「またどこかでお会いできたらうれしいです」なんて言葉を添えたら、先生との良いご縁が、きっとずっと続いていきますよ🌷
小学校転校に伴う保護者の挨拶と準備のポイント
小学校転校に伴う保護者の挨拶と準備のポイントについて解説します。
転校が決まると、学校や担任への連絡だけでなく、周囲の人への気配りや準備物のチェックも必要になりますよね。
特に「誰に」「いつ」「どんな形で」伝えるか――
これがうまくいくと、お別れも気持ちよく進められて、子どもにとっても前向きな経験になります。
ここでは、転校時にやっておいてよかった!と思えるような、保護者目線のリアルなアドバイスをお届けします♪
①連絡帳の文例をもう一度チェック
ここで、これまでご紹介した連絡帳文例を、まとめて振り返ってみましょう。
状況ごとに使い分けできるように、コピペOKのテンプレ風にして整理しました👇
転校が決まりそうなとき
いつもお世話になっております。
まだ正式ではないのですが、来月以降、夫の転勤に伴い転居する可能性が出てまいりました。
詳細が分かり次第、改めてご報告させていただきますので、何卒よろしくお願いいたします。
転校が決まったとき
お世話になっております。
このたび○月末に○○市へ引越すことが決まり、○○小学校へ転校することとなりました。
短い間でしたが、先生の温かいご指導のおかげで、毎日楽しく学校生活を送ることができました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
子どもの心境についての一言
転校を前に、本人も少し寂しさや不安を感じているようです。
引き続き温かくご配慮いただけましたら幸いです。
この3パターンをベースに、自分の言葉で少しアレンジするだけで、十分に伝わる挨拶文になります。
形式にとらわれすぎず、あたたかく、丁寧なトーンでまとめるのがコツですよ♪
ちなみに私は、これらをメモ帳に保存しておいて、他の保護者にも共有したことがあります。
「こんな書き方でいいんだ!助かる~」と喜ばれました☺️
②保護者会への連絡のタイミング
学校関係者への連絡がひと段落すると、次に気になるのが「保護者会」や「ママ友」への連絡タイミング。
これが意外とデリケートで、「早すぎても変に気を遣わせるし…」「遅すぎると失礼かな?」と悩みますよね。
基本的には、担任の先生に伝えたあと~1週間以内が目安です。
【連絡タイミングのおすすめパターン】
| 相手 | タイミング | 手段 |
|---|---|---|
| 仲良しのママ友 | 学校への報告と同時期 | LINE・SNS・対面など |
| 保護者会やPTAメンバー | 転校が確定後すぐ | 会議・LINEグループなどで一言 |
| 知り合い程度の保護者 | 無理に連絡しなくてOK | 子ども伝いで自然に伝わることも |
時間が合わないときは、気軽なメッセージで大丈夫です。
例として、こんなLINEメッセージも自然でおすすめ👇
ちょっとお知らせがあるのだけど…
実は来月から引越しが決まって、〇〇が転校することになりました!
急なお話で驚かせてごめんね。仲良くしてくれて本当にありがとう😊
ちなみに私のときは、仲良しのパパ友2~3人にはSNSで個別にメッセージを送りました。
「えー!寂しくなるけど、応援してるよ!」なんて返信がきて、お別れの寂しさもちょっと和らぎました。
逆に、保護者会のメンバーには、会合のときに一言だけ添える程度でOKでしたよ。
無理に全員に報告しようとしないで、「必要な人に丁寧に」がちょうどいいんです♪
③クラスメイトへの配慮と注意点
転校するお子さんにとって、クラスメイトとのお別れは大きな心の節目。
それと同時に、残される側の子どもたちにとっても、大切な“お別れの経験”になります。
だからこそ、配慮と段取りがとっても大事なんです。
-
お別れを「前向きなもの」にしてあげる
→「寂しいけど、新しい学校でも頑張ってね!」というムードにするのが理想です。 -
話すタイミングは担任と相談
→子ども自身の気持ちに合わせて、クラス発表の時期を調整することも可能です。 -
プレゼントや手紙のやりとりは“自由参加”で
→無理に用意させるより、「渡したい子だけ」がベスト。 -
お別れ会の内容も簡素でOK
→発表や手紙の時間が少しあるだけでも、いい思い出になります。
たとえば、我が子の転校時は「前の週に担任から発表 → 翌週にお別れ会」という流れでした。
担任の先生が「“寂しい”より、“応援したい”気持ちで送り出せるように」と工夫してくださって、
教室があったかい雰囲気で包まれたのを今でも覚えています。
ちなみに、クラス全員分のギフトなどは必要ありません!
最近は、何もしないのが主流です。
心配なら、担任の先生に事前確認すると安心ですね♪
④転校初日の親の付き添いは必要?
転校初日は、まさに「子どもにとって最大の緊張日」です。
新しい友達、知らない教室、初めての先生…
どれをとってもドキドキが止まりません。
そんなとき、親が付き添ってあげると、子どもにとって大きな安心材料になります。
| 付き添いのポイント | 内容 |
|---|---|
| 基本的に付き添いOK | 朝の登校〜教室まで一緒に行く保護者多数 |
| 付き添い後の流れ | 職員室で挨拶 → 子どもは教室へ → 保護者は下校 |
| 学校のルール確認 | 前もって「登校初日は親も付き添ってよいか」確認しましょう |
とくに1年生〜3年生くらいの低学年は、付き添いがあるとグッと安心感が増します。
私の娘が転校したときも、「一緒でよかった…」とホッとした顔をしていました。
ただし、高学年だと「付き添いはちょっと恥ずかしい…」という子もいますので、
本人の気持ちを尊重して「どうしたい?」と一度聞いてあげてくださいね♪
親の立場としては、“そっと見守る応援団”の気持ちで、付き添いに臨むのがいいかもです☺️
⑤転入先への挨拶の仕方と準備リスト
転校前の準備に加えて、実はとっても大事なのが「転入先への最初の挨拶」です!
ここでの印象が良いと、その後の手続きもスムーズで、子どもも安心して通えるようになります。
【転入先での初回挨拶の流れ】
-
職員室を訪ね、受付で名乗る
→「○○区から転校してきました△△の保護者です」と一言。 -
担任の先生や教頭先生にご挨拶
→丁寧に名刺がわりのご挨拶。「よろしくお願いいたします。」 -
手続き書類の提出&説明を受ける
→必要書類の確認や教科書の対応など。
【準備しておくと安心な持ち物リスト】
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 在学証明書 | 転出元の学校からもらったもの |
| 教科書給付証明書 | 教科書配布のために必要 |
| 転入通知書 | 役所で発行される書類 |
| 印鑑(必要なら) | 書類にサインが必要な場合あり |
| 保護者の身分証 | 学校によって求められることも |
| 手提げ袋など | 新しい教科書などを持ち帰るために便利 |
わたしが転入先に行ったときは、事前に電話でアポをとってから伺いました。
そのおかげで、教頭先生が丁寧に対応してくださり、
「ご連絡いただいていたので準備できていました」と言ってもらえて、とてもありがたかったです!
最初の印象って、本当に大事なんですよね…!
⑥引越しはがきで伝えるべき情報とは
転校が落ち着いてきたら、次に気になるのが「引越しはがき」や「転居のお知らせ」。
これはママ友や先生、お世話になった方々に改めてご挨拶したいときにとっても便利です。
特にSNSをあまり使わない世代の方には、心のこもった紙のはがきが喜ばれますよ♪
では、引越しはがきには何をどこまで書けばいいのでしょうか?
基本の構成と注意点をご紹介しますね。
引越しはがきに書くべき基本項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| あいさつ文 | 「ご無沙汰しております」「お元気でお過ごしでしょうか」など |
| 引越し日と転居先住所 | 正確に・番地まで丁寧に |
| 転校先の学校名(任意) | 学年・クラスは書かなくてもOK |
| 転居理由(簡単に) | 「転勤のため」「家を購入したため」など |
| 子ども・家族の近況 | 新しい環境での様子を一言添えると温かい印象に |
| 今後のお付き合いのお願い | 「これからもよろしくお願いします」など |
はがき文例(カジュアルver)
写真付きのはがきを作るご家庭も増えていて、子どもの笑顔や新居の様子を入れると、とっても喜ばれるんですよ~!
ちなみに私は「しまうまプリント」のネットサービスで作成しました📸
安くて簡単、そして発送までお願いできたのでめちゃくちゃ助かりました!
“会えなくてもつながっていられる”って、やっぱり嬉しいですよね。
⑦転校後も安心して過ごすための工夫
転校は、転校して終わりではありません。
実はその後こそ、子どもが安心して新しい生活に馴染めるかが大切なフェーズなんです。
環境がガラッと変わることで、緊張・不安・孤独…いろんな感情が出てくる時期でもあります。
保護者としては、そばで見守りつつ、少し先回りして心をケアしてあげたいですね。
【転校後にできるフォローの工夫】
-
学校での様子をこまめに聞く(でも無理に聞き出さない)
→「今日は何が楽しかった?」という聞き方がおすすめです。 -
新しい友達の名前が出てきたらポジティブに反応する
→「○○ちゃんと仲良くできてよかったね!」 -
前の学校の友達と手紙やビデオ通話でつながる時間を作る
→懐かしい繋がりがあると、心が安定します。 -
頑張りを褒める場面を増やす
→ちょっとしたことで「よくがんばったね!」と伝えるだけで、自信に。 -
無理に溶け込ませようとしない
→「マイペースで大丈夫だよ」と言ってあげることで、安心感が倍増!
転校して3週間後くらいって、ちょっと疲れが出やすいんですよね…。
わが家も、最初はウキウキしていた娘が、急に「なんか学校行きたくない…」と言い出したことがありました。
でも、「いまは頑張ってる途中だよね」って一緒におやつを食べながら話したり、週末に家族で近所のカフェに行ってリラックスしたり。
少しずつ“新しい暮らし”に慣れていけるようサポートしました🍰
大事なのは、環境の変化に気づいて、寄り添うこと。
それがあれば、どんな場所でも子どもはちゃんと笑顔になれますよ♪
小学校の転校時の連絡帳の書き方のまとめ
小学校の転校時、保護者が担任へ連絡帳で挨拶する際の正しい書き方は、まず「転校が決まりそうな段階」で一度報告し、
転校が正式に決まったらすぐに再度詳細を伝えるのが基本です。
この2ステップが、担任の先生にとっても分かりやすく、配慮を得やすいポイントになります。
連絡帳に書く内容としては、引越しや転校の時期・理由・新しい小学校名(わかる範囲)、
そして子どもの気持ちや変化、今後の手続きへのお願いなどが中心です。
特に子どもが不安や緊張を感じている場合は、連絡帳でその旨を簡潔に伝えておくことで、担任の細やかなサポートが受けやすくなります。
挨拶の書き方は、「ご指導ありがとうございました」「毎日楽しく通えたのは先生のおかげです」
といった具体的な感謝の気持ちを、自分の言葉で丁寧に書くことが重要です。
例文をそのまま使うのではなく、自分の子どもの様子を踏まえてアレンジすると、より心のこもった文面になります。
また、保護者としての配慮も大切です。
クラスメイトへの伝え方は先生と相談しながら、無理なく自然な形で行いましょう。
ママ友や保護者会への連絡は、担任への報告後すぐが目安。
必要な相手だけに丁寧に伝えればOKです。
引越し後も、転入先の先生への最初の印象が大事。
書類を整え、笑顔と丁寧な挨拶を忘れずに。
そして、転校後も子どもの様子を見守る姿勢が何よりのサポートになります。
「今日は楽しかった?」と声をかけるだけで、子どもはホッとするものです。
つまり、小学校の転校において、連絡帳での書き方や担任への挨拶は、保護者としての誠意が見える大切な行動。
本記事の例文やポイントを活用すれば、気持ちのよいお別れと、新しいスタートを切るための準備が万全になります。